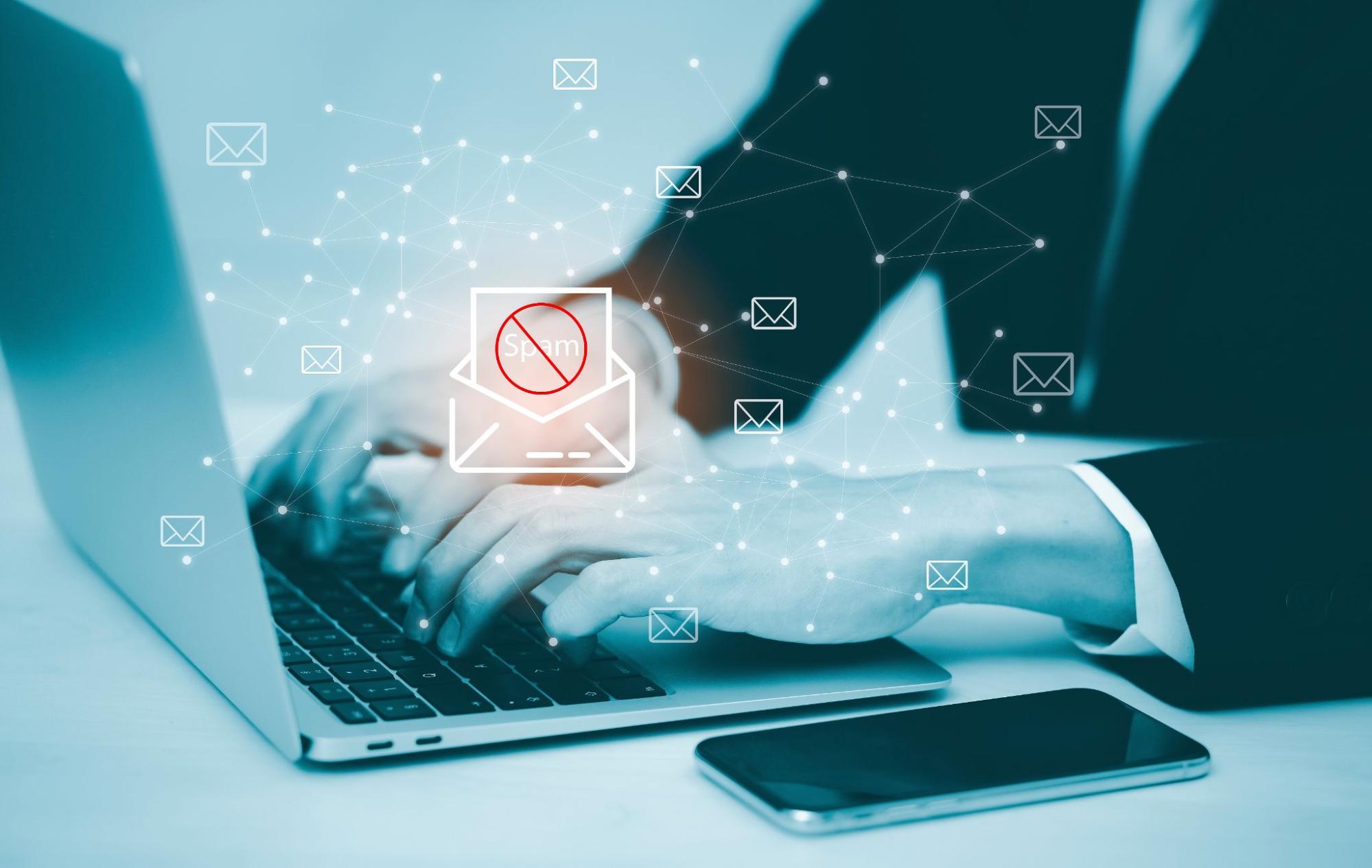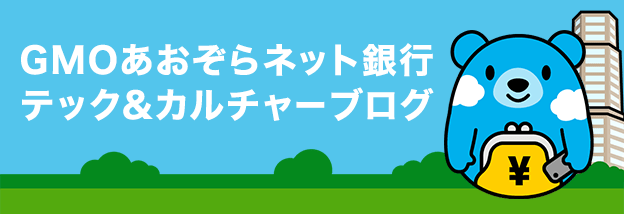偽サイトを使った攻撃手口はさまざまです。個人だけでなく、企業がそのリスクにさらされるケースも少なくありません。
偽サイトとは、正規のWebサイトを模倣し、ユーザーの情報を不正に取得するフィッシングサイトのことです。
個人情報や金融情報の詐取を目的とし、企業にとっても深刻な被害リスクをもたらします。
しかし、適切な対策を講じることで、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。
この記事では、偽サイトの特徴や攻撃手口、企業が取り組むべき対策について解説します。
目次
[ 開く ]
[ 閉じる ]
偽サイト(フィッシングサイト)とは?

偽サイトとは、正規のWebサイトに似せて不正に情報を詐取するフィッシングサイトのことです。
偽サイトのほとんどは、ユーザーの個人情報や金融情報を盗み取る目的で設計されています。
インターネットを利用する個人ユーザーだけでなく、企業が警戒すべき偽サイトも多数あり、その被害リスクは多岐にわたります。
偽サイトは巧妙に作られているため、見分けるのが難しいケースも少なくありません。
ユーザーを欺くための手口も年々高度化しています。企業は常に最新の動向を把握し、適切な対策を講じる必要があります。
偽サイトを使った攻撃手口

偽サイトを使った攻撃手口はさまざまです。攻撃手口の特徴を理解すれば、効果的な対策を立てやすくなります。
ここでは、偽サイトを使った主な攻撃手口を3つ紹介します。
電子メールやメッセージ機能を使った誘導
攻撃者は信頼できる組織を装い、リンク先が偽サイトである電子メールを送信します。これをフィッシングメールと言います。
メール本文には、「あなたのアカウントに不正アクセスがありました」「お客さまのアカウントはサービスを更新できませんでした」など、ユーザーを騙すための巧みな言葉が並びます。
これらのメールには緊急性を煽る内容が多いため、信頼できる組織からのメールであっても、不自然な内容や緊急性を煽る言葉が並んでいたら警戒が必要です。
また、SMSなどのメッセージ機能を使って、偽サイトへの誘導を図るケースもあります。
SNSを使った誘導
SNSプラットフォーム上で偽のアカウントを利用し、ユーザーを偽サイトに誘導する手口も存在します。
攻撃者は、有名企業や著名人、親しい友人などを装い、親しみやすいコンテンツを投稿して誘導するため注意が必要です。
近年では、著名人の顔写真を使った広告詐欺が流行しており、著名人やSNSの運営会社から注意喚起が行われています。
これらの手口により、金銭をだまし取られるリスクがあるため、アカウントの信ぴょう性を十分に確認し、不審なリンクはクリックしないことが重要です。
企業側も自社を装った偽アカウントの監視と、ユーザーへの注意喚起が求められます。
偽のURLを使った誘導
偽サイトの中には、見た目が正規のURLに酷似しているものもあります。
例えば、「www.example.com」という正規のURLを、「www.exampIe.com」(小文字のLの部分が大文字のI)と表記するなど、わずかな違いを見抜くのは容易ではありません。
このような偽URLをクリックしてしまうと、知らないうちに偽サイトに誘導され、個人情報などを盗まれる危険性があります。
URLを確認する習慣を身につけ、少しでも不審に感じたら、直接アドレスを入力するなどの対処が必要です。
偽サイトによる主な被害リスク

偽サイトによる被害は個人だけでなく、企業にとっても深刻なリスクをもたらします。
具体的には、以下のような被害リスクが考えられます。
▼偽サイトによる主な被害リスク
- 財務情報の盗難
- 個人情報の漏洩
- 企業の信用失墜
- 顧客との信頼関係の崩壊
- 法的な責任と罰則の発生
偽サイトで個人情報や財務情報が盗まれると、不正な引き出しや購入などの二次被害に繋がる恐れがあります。
また、企業の機密情報が流出した場合、競争力の低下や事業の停滞など、深刻な影響を及ぼすでしょう。
個人情報保護法などの法規制に抵触する可能性もあり、その場合は法的責任や罰則を受ける危険性が高まります。
【従業員向け】企業が取り組むべき偽サイト対策

企業は従業員を対象とした偽サイト対策を講じることが重要です。
まずは、企業が取り組むべき偽サイト対策を従業員向けに解説します。
OSやシステムのアップデートを徹底する
常に最新のセキュリティパッチとアップデートを施すことで、脆弱性を減少させることができます。
脆弱性とは、サーバーやシステムに存在するセキュリティ上の弱点のことです。
OSやソフトウェアのバージョンが古いと、既知の脆弱性を突かれるリスクが高まるため、アップデートの徹底が欠かせません。
ついアップデートを忘れてしまうようなら、自動更新機能を有効活用しましょう。
従業員教育を行う
社内の従業員に対して、フィッシング詐欺や偽サイトの見分け方を定期的に教育することが重要です。
教育する際には、以下のようなポイントを踏まえると良いでしょう。
▼従業員教育を行う際のポイント
- 不審なメールの特徴を具体的に伝える
- 安全なURLの見極め方を教える
- 個人情報の取り扱い方を指導する
教育プログラムを講じることで、従業員1人ひとりのセキュリティ意識を高めることができます。
また、新しい攻撃手法についての情報を随時共有し、常に最新の知識を身につけられるようにする工夫も大切です。
セキュリティ対策ソフトを導入する
セキュリティ対策ソフトの導入も偽サイト対策に有効です。
アンチウイルスソフト、ファイアウォール、Webフィルタリングなどの機能により、偽サイトへのアクセスをブロックできます。
また、不審なメールやファイルを検知し、リアルタイムで警告を発することで、被害を未然に防ぐことが可能です。
セキュリティ対策ソフトは、企業資産を守るための重要な防御線となります。
導入する際には、提供するベンダーの信頼性を確認し、よりセキュリティ性が高いサービスを選択するようにしましょう。
【顧客向け】企業が取り組むべき偽サイト対策

偽サイトの対策は従業員にだけでなく、顧客に対しても行う必要があります。
ここでは、顧客を偽サイトの被害から保護するために企業が実施すべき対策を紹介します。
顧客に対して注意喚起を行う
自社の偽サイトが確認できた際には、顧客に対して注意喚起を行いましょう。
偽サイトの存在とそのリスクについて、積極的に情報提供をすることで被害の拡大を防ぐことに繋がります。
この際、顧客にはメールの内容や偽サイトの特徴を具体的に伝えるようにしましょう。
また、URLの確認方法、不審なメールへの対処法、パスワード管理の重要性などを伝えることで、顧客自身のセキュリティ意識を高めることができます。
偽サイトを検知・削除する
定期的に偽サイトを検出し、発見した場合は速やかに削除することが求められます。
自社のブランドを不正に利用するサイトを放置することは、顧客の信頼を損ねるだけでなく、法的責任を問われる恐れもあります。
自社のブランドを確実に保護するため、できる限り早めに偽サイトを削除しましょう。
▼偽サイトを削除する主な方法
- 公式サイトの運営者自身が行う
- 専門機関に削除依頼を行う
- テイクダウン代行の事業者に依頼する
検知には監視ツールの導入や検索エンジンの活用などが有効ですが、自社のみで対策が難しい場合は、専門のサービスへの依頼も検討すべきでしょう。
迅速な対応により、被害の拡大を防ぎ、自社と顧客の安全を守ることができます。
警察への相談を検討する
偽サイトに関連する犯罪活動を確認した場合、警察や関連機関への相談を検討しましょう。
フィッシング詐欺やなりすまし、著作権侵害など、違法行為が疑われる際には、速やかに相談しましょう。
法的手段を活用して迅速に対応することで、犯罪拡大の阻止を図れます。
相談窓口は都道府県によって異なるため、警察庁の「フィッシング対策」のページからフィッシング報告専用窓口に相談してください。
偽サイトの検知・削除ならGMOブランドセキュリティにお任せ

画像引用元:GMOブランドセキュリティ
偽サイトの検知・削除を行いたいなら、「GMOブランドセキュリティ」へのお問い合わせをご検討ください。
同社の「GMOブランドサーベランス」では、ブランドを脅かすドメインネーム・ウェブサイト・マーケットプレイス・SNSといったオンライン上のブランド毀損を、AIを活用して手間とコストを抑えながら把握・分析した上でブランド侵害のあるサイトのテイクダウンが可能です。
ブランド侵害の「検知・監視」と、ブランド侵害に対するサイトの「テイクダウン」までをワンストップでサポートするのが大きな特長です。
世界中の主要なドメインネーム・ウェブサイト・マーケットプレイス・SNSサイトを網羅しているため、複数のサービスを利用する必要がありません。
さらに、経験豊富なメンバーが貴社の状況を確認し、監視対象に関する戦略立案やリスク排除のためのポイントをわかりやすくお伝えします。
また、すでに偽サイトや模倣品がある企業の方は、「GMOエンフォース1」を利用することで、安価かつスピーディーに権利行使が行えます。
ブランド保護の重要性が増す今、同社のサービスを活用し、安心してビジネスに専念できる環境を整えてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、偽サイトの特徴や攻撃手口、企業が取り組むべき対策について解説しました。
偽サイトによる被害は、個人情報の流出だけでなく、企業の信用失墜や法的責任など、多岐にわたります。
多角的なアプローチを取ることで、偽サイトによるリスクを効果的に防ぐことが可能です。
偽サイトの検知・削除を行いたい企業様には、「GMOブランドセキュリティ」のサービスがおすすめです。ブランド侵害の監視からリスク排除までをワンストップでサポートし、効果的なブランド保護を実現します。
文責:GMOインターネットグループ株式会社